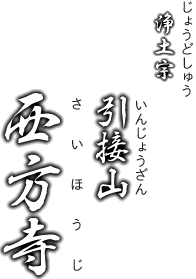西方寺縁起
本尊:阿弥陀如来像
開山:嘉禄二(1226)年
改宗:文禄元(1592)年
当山は清和源氏の遠祖左中将新田大炊介義重公(大光院殿方山西公大居士)を祀って
公の四男義季(徳川の祖)の舎弟五男経義(出家して祖底襌師)が治承3年(1179)に
これより東南二キロ長老尾(当山旧跡)に庵を結んで創まる。
嘉禄二年(1226)には本尊十一面観世音菩薩と公の霊牌と霊剣「小安丸」をまつって入佛供養を修す。
それより「山の寺」「寺家」と四遷して享保14年(1729)に現在地に移る。
明治の初めには勝海舟 大隈重信 品川弥二郎他多数の重要人物が来訪している。
又、昭和19年より21年に至る間 大本山増上寺黒本尊(徳川家康公守本尊)が
第二次世界大戦の戦火をのがれて当山経蔵に遷座せしことは特筆すべき事跡である。
甲斐百八霊場 第二十八番札所
Wikipedia
郡内三十三番観音霊場 第八番札所
富士山NET
年中行事
- 1月
-
1日修正会
-
24日御忌会
- 3月
-
日春彼岸会
- 5月
-
8日花まつり(灌仏会)
- 6月
-
19日開山忌(守本尊祈願会)
- 8月
-
日盂蘭盆会
- 9月
-
日秋彼岸会
- 11月
-
14日十夜会
- 12月
-
31日除夜(浄焚会)
文化財
阿弥陀種子板碑
板碑は卒塔婆の一種であり、板状の石で作られる。
石の頭部を三角形にし、その下に二条の切り込みを作りさらにその下に梵字(サンスクリット)、仏像、銘文などを刻むのが普通で、鎌倉中期以降供養塔として盛んに作られた。
所蔵の板碑は大小二基あり、大きい方は鎌倉時代の弘長元年(1261)に作られたもので、県下最古のものであり、碑高は91センチ、緑泥片岩で作られており、
身部の上方に雄大な筆致を示す薬研彫の弥陀種子(阿弥陀仏を表す梵字)を蓮華上に安置したもので、弘長の書体や干支の位置、割書などにもよく時代の特色を示している。
もう一基は碑高43センチで、石材は玢岩であり南北朝時代の延文6年(1361)の作で、大きい板碑の100年後に作られたものである。
二基とも、向原地区の東方にあった西方寺旧地の土中にうもれていたが、大正12年の関東大震災の土砂崩れによって発見されたものである。
ご案内
十一面観音
観音堂には別名 身替観音とも言われる十一面観世音菩薩の尊像が祀られる。
この十一面観音は、開山の父義重公が源氏代々の守本尊として信仰したもので開山時から祀られ、
爾来800年当時の秘仏として地方大衆の守本尊となり、天下泰平、万民和楽の祈願を続けている。
位牌堂

経蔵と水子地蔵

金網地蔵

西方寺にあるお地蔵さんには金網がはってあるが、これは昔、夜になるとお地蔵様が歩き出して困ったため、金網を張ったと言われている。
交通案内
引接山 西方寺
いんじょうざん さいほうじ
〒403-0002
山梨県
富士吉田市
小明見二丁目18-27
TEL:
0555-22-0299
FAX:
0555-22-0499
google map